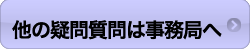文学部
Q1:男で文学部卒というのは将来の就職活動で大変になるのでしょうか。
A:自分が実際に就職活動をしてみて感じたことは、自分がどの学部にいるのかということよりも自分が何を勉強したいか、そのためにどんな努力をしてきたのかということをちゃんと考えてこれた人を求めているのではないかと思いました。
あとは僕の周り英文科学生でも旅行会社やメーカー、航空会社やIT関連にあと同じ編入の仲間の中では金融業界に内定をもらっている人もいます。なので今では学部はそんなに重要なことではないと思っています。
なのでじっくりと考えて答えを出してください。
Q2:入学後第二外国語は必修でしょうか?
A:第二外国語は必修です。単一言語で8単位必要になります。
Q3:口頭試問ではどういった質問がされるのでしょうか?
A:口頭試問は何組かのグループに分かれて2人の面接官に試問されるのですが、どうやら日本人の面接官だけのグループと日本人と外国人の面接官のグループがあるみたいです。主に質問してくるのは日本人の面接官ですが、外国人の面接官も普通に英語で質問してくるので事前に準備しておいた方が落ち着いて答えられると思いました。
ですが自分の場合は、面接中にしっかりと英語で受け答えできていたかというとそうでもなく、緊張していたのもあってかうまく受け答えすることができませんでした。なのでたとえ英語がうまくしゃべれなくても、自分がどうして編入したいか、なぜ同志社大学でないとだめなのかなど、しっかりとした考えがあれば問題ないと思いますよ。
A:哲学科の口頭試問は特に身構えなくても大丈夫ですよ。今まで大学でどのようなことを学んでいたか、それから、なぜ同志社の哲学科へ編入を望んでいるかなど、聞かれます。
三年次の編入なのであれば、卒業論文へむけて取り組みたい専門のテーマなどをはっきりと(おおまかな現時点での自分の関心事の内容を)説明できればよいでしょう。また、なぜ他大学でなく同志社大学の哲学科で編入をして学びたいか、学ぶ必要があるかということを明確に説明できるようにしておくと大丈夫でしょう。
Q4:専門科目の勉強ってどのようにしていましたか?
A:専門書を読むといいとおもいます。英文学科は大きく分けて『英米文学分野』と『言語学分野』に分けられます。『英米文学分野』では欧米の小説・劇・絵画などを扱い欧米の文化や歴史への理解を深めます。文化的思想や社会情勢などが作品にどのような影響を与えたかを研究します。もうひとつの『言語学分野』では「英語」という言語を研究対象にします。語順や言い回し、語彙、比喩など言葉を中心に研究対象は様々あります。
このように大きく文学と言語に分かれる英文学科の中で私は言語学を専攻しています。言語学の中にも心理言語学、比較言語学、応用言語学、社会言語学などいろいろありますが、私の専攻は社会言語学です。したがって、以前お答えした専門書の多読というのは「言語学入門」や「社会言語学」というような本を読んだということです。
専門書を読むことのメリットは2点あると思います。1点目は編入学後の方向性が明確になり面接で説得力を持って説明できることです。(口頭試問では受験生の専門によって面接官が変わるようです。)2点目は、概論レベルの問題対策になることです。私が受験した際の小論文のテーマに、言語学分野に含まれる英語学で有名な理論が出題されました。研究者の間でどのような議論がなされ、現在どちらが有力とされているのかを知っていたのでとても書きやすかったです。
注意していただきたいのですが、以上のことは受験対策としてこうしなければいけないというものではなくあくまでも私の体験談です。私は英語力に自信がなかったので専門知識で補強したという側面も大きかったと感じています。合格した方の中には、専門書を読まなかった人もいますし、違う分野から来た人もいます。対策の仕方はそれぞれです。私は予備校に通っていなかったので受験のセオリーは分かりません。やったほうが良いと思うことをやってきただけなので、Aさんもご自身が行うべきだと考えたことをぜひ実践してみてください☆ご理解いただけましたでしょうか?
A:私は文学部英文学科に編入学したので、専門科目は英語で、内容は長文読解、英作文、essayだったと思います。その対策として短大のゼミの先生の指導のもと長文、文法、英作の問題集を繰り返し解きました。また、専門書を多読し、専門に関する授業を積極的に取って専門知識を増やすようにしました。
受験の時に専門分野で有名な理論がessayに出題されたので、個人的には本や授業で勉強しておいて良かったと本当に思いました。
近くに専攻したい分野を専門とする先生がいらっしゃるのならば、指導の依頼を申し出てみるといいと思います☆
Q5:哲学科への編入試験では外国語文献読解と書かれています。みなさんは、どのような勉強をしましたか?
A:外国語文献読解では、英・独・仏の三ヶ国語から自分の得意な言語を選ぶことができます。
選択した語学に関してある程度の力があれば大丈夫ですよ。(募集要項をもらうと、昨年度の過去問ももらえると思うので見てみてください。)
私は(英語を選択しましたが)入試のための勉強は特にしていません。
あえていうなら、一般教養レベルの哲学に関する知識がある方が読みやすい問題がでるので、一般向けの西洋哲学の概説書などをよんでおくと対策になると思います。
Q6:英文学科は英語が得意な人たちばっかりなのでしょうか?
A:確かに合格者の中にはTOEICのスコアがとても良い方もいますが、決してそれがすべてではありませんよ!!!!ホントに!試験において大事なのは解答の中身だと思います。完璧な英語で解答できていても内容が浅かったり、的外れだったりすれば評価は低いはずです。反対に、完璧な英語ではないけれど内容が深く、的を射ている解答であれば前者よりも高い評価が得られると思います。
だから、設問に適切に答えられる程度の語学力と確かな知識があれば帰国子女にもTOEIC900点台の人にも勝てる可能性は十分にあると思います!!!私自身、人に誇れるような語学力はありませんでしたが合格することができたので、帰国子女とかTOEICとか関係ないと強く思います!!最後まで諦めずに頑張ってみてはいかがでしょうか☆
Q7:英米文学科はどのように勉強したほうがいいですか?
A:試験内容は、英語・小論文・英作文・面接です。英語のテスト形式は一般入試試験とあまり変わらなかったので、赤本で過去問を勉強するといいと思います。
法学部
Q1:三年次編入なのですが, 履修するべき講義は京田辺キャンパスまで行かなければならないのですか?
A:語学科目を除く必修科目、つまり法律系の1・2年次必修科目は京田辺キャンパスでしか開講されておらず、京田辺での受講になると思われます。
大変だとは思いますが、同志社大学の1・2年次必修科目では、知的財産法、国際私法、労働法など他大学では必修科目としては取り扱わないような科目まで開講しており、様々な法律に触れられる機会でもありますし、先生方の講義もわかりやすいので、非常に勉強になりますので、辛いとは思いますが、
京田辺キャンパスまで行って、受講する価値はあると思います。
Q2:政治の科目はどのような問題がでるのでしょうか?
A:同志社政治学科の過去問を見る限り、毎年政治学の問題は論述問題が二つ出題されており、そのうち一つは国際政治の観点からの問題です。(2009年度だけ例外ですが。)有斐閣の「国際政治学をつかむ」という本を読まれてみてはいかがでしょうか。
Q3:大学の成績は筆記試験と同等またはそれ以上に評価されるのでしょうか?
A:このご質問に関してましては何とも言えませんが、大学の成績が筆記試験以上に評価されるということはないと思います。
やはり筆記試験が一番重要なのは確かです。
ただ編入後の単位の互換認定のことを考えると、1単位でも多く取得されていたほうが良いと思います。
Q4:専門書はどのようなものをお読みになられましたか?
A:僕の場合は、まず専門論文対策としては、伊藤正巳=加藤一郎編『現代法学入門[第4版]』(有斐閣双書 2008)を読み込んでいました。次に語学試験対策としては、Japan timesやNewyork timesの電子版などを訳していました。
A:有斐閣の「国際政治学をつかむ」という本を読まれてみてはいかがでしょうか。
あともう一冊政治学の本が必要でしょうが、そっちはいい本をしらないので・・・。シラバスにのっていた「はじめて出会う政治学」は少し編入にはレベルが低いイメージです。
法学も視野にいれておられるなら有斐閣の「法学入門」がいいとおもいます。
Q5:論文試験の解答用紙には何文字くらい書けばいいでしょうか?
A:5枚のうち3枚書き切らなかったです。むやみやたらに解答用紙を埋めたいかもしれないですが、法学部の論文はきちんとした論拠を挙げて説明出来れば解答用紙の字数は気にしなくても良いと思います。
あまりにも字数が少ないときちんとした論拠が足りないかもしれないですが。。。
Q6:どのような勉強をしましたか?
A:論文試験は、かなりマイナーですが、「最強の課題式論文対策」という地方の予備校CRSが出版している本をお勧めします。
小論文というのは、採点してくれる人がいないと、なかなかうまく書けるようにはなりません。通信講座で小論文を採点してくれるところもありますので、ご利用になってはいかがでしょうか。 もし、小論文を自力で勉強するとなると、文の書き方を理解し、最近の論点をひたすら覚えるしか無いと思います。
英単語に関しましては、単語帳を覚えるのではなく、JAPAN TIMES 等の英字新聞をひたすら読み、わからなかった単語をメモして、それを覚えるといったやり方の方が効率的に単語力がつくと思います。
Q7:論文の解答用紙の大きさはどのくらいになりますか(時間的に余裕はありますか)?
A:1題目はA4サイズ1枚分の解答欄で、2題目はA4サイズ5枚分ありました。
1題目は解答欄を十分に埋められるものの、2題目はA4サイズ5枚分を書ききるのは不可能に思えました。私の場合は、2題目は3枚ほどしか書きませんでした。
私が思うに、法的根拠をきちんと挙げ、論理的な文構造を作り上げるのが、法律の論文試験を突破するカギであるように感じました。
時間的余裕は私はあるように感じましたが、そうは思わなかった人もいるようです。
私は問題に関連する法的知識を書き加え、他の受験生との差別化を図ろうと努力しました。確かに論文は個々の差が如実に現れやすい分、私も論文が重要であると思います。ただ英語は他の受験生もきちんと仕上げてくると思うので、ここで点数を落としてしまうと、厳しい戦いになるのは必至です。したがって英語も疎かにせず確実に正答していけるよう心がけて欲しいです。
またこれは補足としてですが、試験自体をしっかりとこなすことは大前提ですが、志望理由書にも是非凝っていただきたいと思います。志望理由書がすばらしいものであれば、採点の際の試験官のあなたに対する印象も多少なりとも変わってくるはずです。
最後になりましたが、編入試験のあなたのご健闘をお祈りします。頑張ってください。
商学部
Q1:大体何割くらい取れれば合格できますか?
A:7割くらいです。
Q2:TOEICとか英検のスコアはどれぐらい持っていましたか?
A:英検は今準一級持ってます。
でも関係ないと思います。同期で英語できるのは俺くらいでした、英語はぎりぎり6割できればいいんじゃないでしょうか。
Q3:毎年傾向とか変わってますか?
A:毎年傾向とか変わってますか?そのなかで簿記はかわらないので出来るようになった方がいいですね。3級レベルですし。
Q4:編入は就職で不利になったりってしますか?
A:就職は前にいた大学と同志社をとうして、何をしたかによるとおもいますよ。編入生は編入予備校行って、同志社入って単位とって終わりの人は苦労しますね。たぶん。サークル活動などの実績などがないと。
Q5:どのようなテキストを使いましたか?(英語・専門)
A:自分は予備校にいってはなくて、学校の図書館にある英語の新聞の経済面を読んだりしてました、簿記3級のテキストですね。後の科目は大学で使われるようなテキストを読めば大丈夫だと。
社会学部
Q1:英語の免除はうけましたか?
A;私の受けた教育文化学科ではTOEFL500点以上で英語試験免除でしたので、私は免除されました。
その時の受験生には、TOEFL免除者は私を除いて二人いました。英語試験免除より英語試験を受けて編入される方が多いです。
Q2:どのような勉強をしましたか?
A:学習方法に関してなのですが、金銭的な問題がなければ、編入の予備校に通うことをお勧めします。
というのも、独学で勉強するための指針をつかむのが困難だからです。予備校であれば、実際の過去問を用いて解法を教えて下さるほか、模擬面接や志望理由書の添削を実施しているので、独学に比べて勉強がはかどると思います。
過去問は予備校であれば豊富に取り揃えてありますよ。実際に私も予備校を利用しました。
社会学に関しては、私が予備校で勧められたのは、日本実業出版社から発売されている『社会学がわかる事典』です。
私は社会学の学習はこれを使用しました。
A:英語はどの学部でも「和訳力」がカギになります。
なので、大学受験用の長文問題集で解答冊子に全文和訳が付いているものを買い、ひたすら英文和訳してノートに書いていき、書き終わったら解答冊子を見ながら訳し方が正しいかどうかをチェックしていきます。
なお、正確な訳をするために、英語構文参考書、英文法参考書も併用して、英語特有の技法を身につけるといいです。
倒置、強調構文、関係代名詞の省略などの技法は、知らなければどうしても正確な訳がでないので、しっかりと覚える必要があります。(そういう和訳問題がよく出ます)
長文問題集にはもちろんそれぞれの文に設問がいくつかありますが、辞書でわからない単語を調べながらでも全文和訳が出来上がった状態で「オマケ」として設問を解くくらいの感覚です。
最初の方は時間がかかりますが、正確な和訳を心がけて日々練習していれば、だんだんと読むスピードも上がっていきます。
また、同志社の場合は当日の辞書持込は不可なので、大学受験用の単語帳を使って単語をコツコツ覚えていくといいです。
あと、それぞれの学部の問題によく出てくる、その学部の「専門用語」については、和訳がしっかりできるようになった上で徐々にとりかかれば十分間に合います。(多くの専門知識を問われることはないです)
あと、これはどちらでも構わないですが、自分は夏休みに気を緩めないために河合塾の夏期講習の「英文解釈」という授業を受けていました。
来年になったら、同志社のページから前年度の過去問を入手してみるといいです。 編入専門予備校では何年分かの過去門が置いてあるらしいです。
長くなりましたが、同志社の編入試験の英語は私立の中では相当な難易度があると言われているので、しっかりと勉強しておけば、英語で他の受験生と差をつけることが可能なので頑張ってください。
A:英語対策に使った問題集は1.「基礎 英文法問題精講」と2.「英文法標準問題精講」と3.「英語長文問題精講」がメインでした。まず1をやってから2をひたすら繰り返しましたね、確か。単語はターゲット1900を使ってて、高校時代の先生にターゲットの問題データをもらって確認しながらやってました。私は面接対策として専門用語を覚えました。(大学によっては知識を確認してくる面接もあるので^^;)
経済学部
Q1:どのような教材を使って勉強しましたか?
A:経済学の問題演習なら、やはり公務員試験用の問題集がいいと思います。
私は、「新スーパー過去問題ゼミ2」を使っていました。
各分野の説明とそれに関するたくさんの問題が載っていて、問題も「基本レベル」、「応用レベル」の2つに分かれています。応用レベルはなかなか難しいので、基本レベルだけでも十分だとは思いますが、挑戦する価値はあります。あとは、途中計算や途中説明を書かせる問題がほとんどなので、問題を解く時はノートに途中経過を書くことと、毎年、用語説明が出題されているので、基本的な語句の意味を調べておくといいです。次に英語ですが、経済に関連していてオススメなのは、「速読速聴・英単語 Business1200」です。
工学部
Q1:難易度はどのくらいですか?(対策はありますか)?
A:数学は合計3問で1問目が確率・統計と2問目は微分方程式か線形代数……だったかな? 1問目と2問目は毎年同じ傾向の問題でしたが、3問目は異なっていました。英語はどこが範囲かと言えるほど得意ではないので……。私が受験したときは文化に関する長文問題が出されました。
面接ですが、採点されたばかりの答案用紙を横に問題を作成した英語担当と数学担当の先生方が面接されます。テストの結果についての自己評価と、志望理由、雑談を含めたその他もろもろを聞かれました。嘘をつかず、素直にハキハキと答えていれば問題ないと思います。私の場合、テストの点数は悪かったのですが、面接できちんと話せたのが良かったのかなぜか通りました。
他の学部よりも志望者が少なく、競争率は高くないのであまり気負わずに受けてもらえればと思います(^^
個人的には、試験よりも入学後の方が頑張らなければならないかと思うので、その辺りは覚悟した方がいいかと……。
A:英語は長文読解が中心でした。難易度については比較対象がないので何とも言い難いですが、手のつけられないような問題ではないです。空欄や記入ミスがないようにだけ気を付けて取り組んでください
数学は大問3問で、微分・積分、線形代数、微分方程式、確率・統計の分野から中心に出題されます
私が受験した年は線形代数、微分方程式、確率・統計の3題でした
面接に関しては先に挙がっているコメントにも言及がありますが、入学後の覚悟が問われたのが印象に残っています
政策学部
Q1:どのような問題がでますか?対策はありますか?
A:とにかく、これから試験本番まで、ニュースと新聞を毎日見るということが一番の力になると思います。
自分は経済学部ですが、ニュース、新聞、新書、この3つは大事だと思って学習材料にしていました。
あと、経済学部の場合はミクロ、マクロの計算問題を解く力も必要になるのでそれらをやっていましたが、政策学部はその必要はなく、「経済問題の仕組み」を知ることが重要です、経済問題の仕組みを知る上でその基盤として、初歩的な経済学の勉強はしておいた方がいいということで、経済学の勉強も並行することをお勧めしました。
あと、論文でガツガツと書かされるので、普段から書く力を身につけておいた方がいいと思います。
書く力を身につけるためには、社会問題としてとりあげられているキーワードの語句説明を自分なりにしてみるのが一番いいと思います。
たとえば、ニュースで「こども手当て」という言葉が出てきて、何のことかがわからなければ、インターネットなどで調べながら、「こども手当てとは~」という感じでノートに書いて説明していきます。
あと、できれば予備校などで専門の先生がいるのがベストですが、もしいなければ、親や友達など、身近な人で構わないので、書いたものを添削してもらうと更にいいです。
これから入試までの間、ずっと続ければ、知識も書く力も膨大なものになることは間違いありません。
長文になりましたが、少しでも参考になればと思います、頑張ってください。
単位について
Q1:他学部からの編入した場合、どのくらい単位認定されますか?
A:違う学部からの編入になると単位が30パーぐらいきられてしまうかもしれないので、だきるだけ目指している学部に関係する科目を履修したほうが、いいでしょう。
A:僕の場合は専門学校からの編入でしたので単位認定があまりされませんでしたが、短大や大学から編入した人はたしか50~60単位は認定されていたと思います。
A:私は文学部に編入したのであまり参考にならないかも知れいですが、87単位中66単位認定されました。これでも以前の学校での専攻と今の専攻が同じなのでかなり認められた方です(;へ;)!!
単位認定は粘って交渉するべきですよ!私も2単位上がりましたし♪何年で卒業出来るかも関わってくるので、ここはガツガツ行くべきです!
Q2:編入を考えている場合、どのような科目を履修した方がいいでしょうか?
A:同学部でも他学部系統からでも、目指す学部で履修するような科目をとったほうがいいとおもいます。
Q3:合格後の単位認定面接はどのようなものですか?
A:「単位認定のための面接」は、編入前の大学の単位と同志社大学の講義を照らし合わせて何単位を認めるかを話し合います。緊張感に満ち溢れたものではありません。
事前に学部側がシラバスを参考に認定した単位を提示し、認定しなかった単位に関いて編入者本人と職員、学部ごとの担当教授と話し合います。なので、前の大学で受けた講義の内容を簡単に見とくことは損にはなりませんが、がっつりと知識は問われません。
ただし、ここでの単位数が、学生生活を左右することもあるので、単位を確保したいのであれば粘ってください。面接終了後は入学式ですね。たるさんにお会いできる日を楽しみにしています。
補足
面接終了時に、履修要項などのお土産を渡されます。荷物が増えることだけは覚悟してください。
Q4:同志社にも単位の履修制限があると思うのですが、それは編入生にも適用されるのでしょうか?
A:適用されます。くわしくは事務局に問い合わせください。
Q5:出願条件の単位はどんな単位でもいいんですか?
A:単位については、どれをとっても指定単位を満たしていれば受験資格が与えられますが、入学決定後の単位認定で、できる限りその学部の専門科目を認定してもらった方が後々楽になるので、今通われいてる大学でもできればいきたい学部に関連する科目を多く履修しておいた方がいいです。
とはいえ、専門科目ばかりを履修するのはさすがに疲れるので、あとは、学部共通科目、体育科目、語学科目などを入れれば、認定してもらえます。
etc
Q1:編入会に入るにはどうしたらいいですか?
A:トップページから入会希望の方というところをクリックしてください。
Q2:倍率が高いのですが合格できますか?
A:日東駒専の二次募集の試験も倍率が、20倍とか30倍近くあるのはご存知ですか??落ちてどこの大学もとうらなかった、かそれより低い大学のしか受からなかった人が受けにくるわけです。じゃあ早稲田、慶応に受かった人が倍率が高いからといって、そんな人たちが集まった試験に落ちますか??
倍率は関係ないです。あなたが努力すればいいだけです。
同志社以上の大学に行ってる人は受けにこないんですから。
Q3:皆さんはどのようにしてゼミを決めましたか?
A:A:3回生のゼミは通常、選考などを経て2回生の終わりに決まっているので、編入生がゼミを決めるときには入れないゼミもあるようです。事前に希望ゼミを考えておいてくださいという説明があった上で、入学式後の履修相談で定員に余裕のあるゼミとそうでないゼミを教えてもらい、その場で履修担当の先生と相談してゼミを決めました。その後、希望ゼミの先生にアポを取り挨拶をするという流れでした。私はもともと希望していたゼミに余裕があったので問題ありませんでしたが、込み合っているゼミでも交渉次第で入れるような印象でした。
A:同志社大学のHPに教授のEmailアドレスが載っているので、直接お聞きになってはいかがでしょうか? 私も、去年直接教授宛にメールをしましたが、親切に返事を返してくれましたよ。
Q4:編入したら4年で教職がとれますか?
A:こんにちは、編入して2年で教職とるのは無理ですね。留年しないととれません。
Q5:編入前の学校の成績は反映されるのでしょうか?
A:全く関係ないと思います。自分は18単位でした。しかし学部によっては最低とっておかないといけない単位があるので調べておいてください。
Q6:合格点について
A:合格点は全学部7割くらいと考えていいと思います。
Q7:編入会は京田辺でも活動していますか?
A:メンバーが文系学部の人が多いということがあり、活動を行う際に今出川ですることが多いのですが、京田辺キャンパスでは定期的に集まってランチをしています。
理系学部の編入生や法学、経済、商学部などの2年次編入生が来年もっと増えれば京田辺中心の活動も行えると思います
Q8:今いる学部と違う学部に行く場合留年する確率は高いですか?
A:現在所属している学部と志望している学部が異なる場合、単位のほとんどは一般教養として認定されると思います。事実、経済学部から社会学部へ編入した私はそうでした。
編入後専攻が変わると卒業までに取らなければならない必修、選択科目が抜けている場合が多いので一般の学部生よりも留年の可能性は高いです。そこからは本人のがんばりと、どれだけ単位が認定されるかという運が大きく関わってくると思います。
Q9:学部を併願することはできますか?
A:受付は学部ごとになると思うので併願も可能だとは思いますが、
自分の土俵でない学部を受けるのは大変だと思います。
また、今まで専攻していた学部と別の学部へ入学できた場合でも、
入学後の単位数が足りないなど苦労する場面が出てくると思います。
併願は出来ても、あまりオススメはしません。
自分の行きたい学部を一本に絞って、
その学部に向けた対策を取って勉強されたほうが良いと思います。
Q10:編入試験の合格者は社会人は多いですか?
A:私が見る限り、この大学では概ね大学在籍中の人が編入しています。
大学を卒業してすぐにこの大学に入学された方もおられますが…
法学部の編入試験の形式については申し訳ありませんが、存じておりません。
Q11:編入試験ってむづかしいのですか?
A:一般入試より簡単です、同志社以上の大学の人は受けにきませんし、倍率は高いですが7割とれればとうりますから。
Q12:編入は就職で不利になったりってしますか?
A:就職は前にいた大学と同志社をとうして、何をしたかによるとおもいますよ。編入生は編入予備校行って、同志社入って単位とって終わりの人は苦労しますね。たぶん。サークル活動などの実績などがないと。
Q13:同学部系統じゃないと編入試験に合格するのは難しいですか?
A:全く関係ないですよ。元が短大とか予備校とかの人が多く、元が文学部の人がはいないと思います。どの学部もそうですが、元いってた大学と同じ学部に編入って人は少ないですね(*^◯^*)
Q14:入学前にしといた方がいいことはありますか?
A:入学式前後は履修登録関係でとても忙しかった覚えがあります。履修要項は各学部事務局で事前に入手可能なので早めに準備しておくと良いと思います。また、履修登録はパソコンで行うので下宿される場合は早めにネット環境を整えておくことをお勧めします。(京都では2~4月はネットの工事予約が込み合い時間が掛かります。)